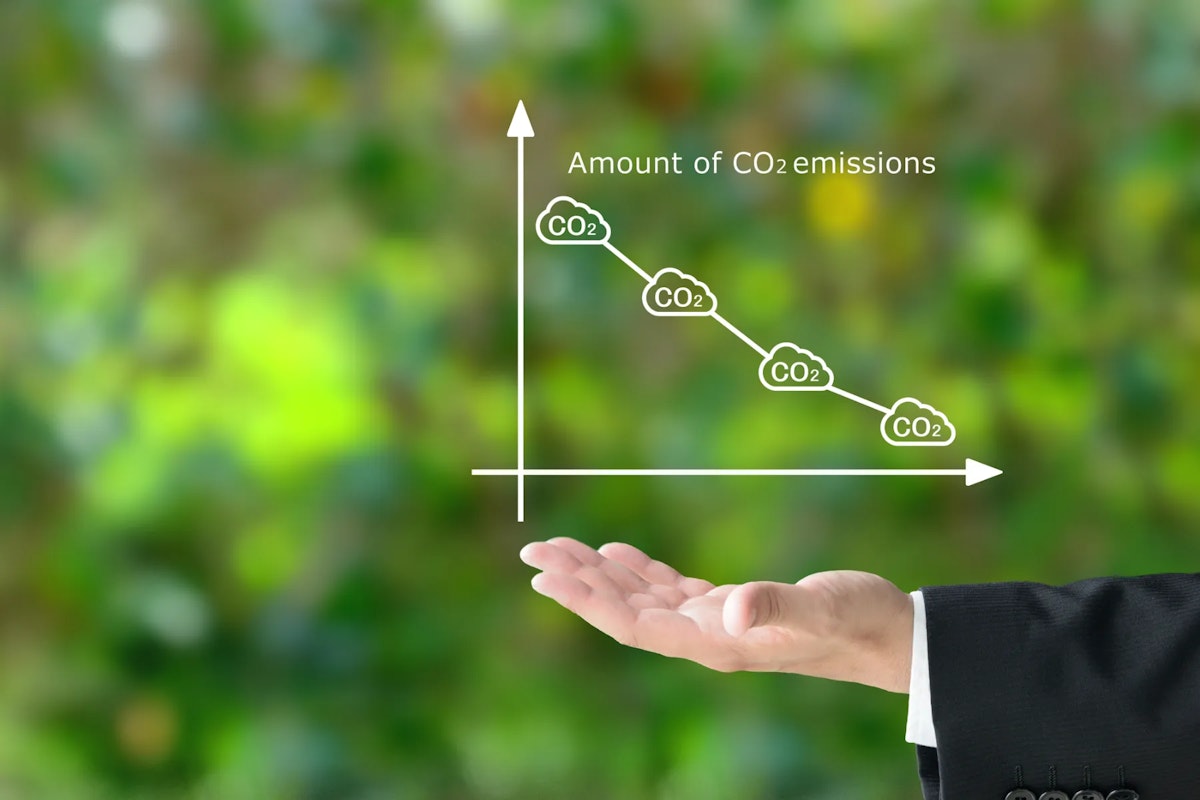なぜ今、企業はCO2を測る必要があるの?
「うちの会社でもCO2排出量を測らなきゃいけないの?」
もしあなたがこう思っているなら、その答えはおそらく「はい」です。なぜなら、CO2排出量の「見える化」は、もはや大企業だけの課題ではなくなってきているからです。
でも、なぜCO2を測る必要があるのでしょうか?簡単に言えば、こんな理由があります。
- 取引先からの要請:大手企業が自社のサプライチェーン全体でCO2削減に取り組む中で、取引先に対してもCO2データの提出を求めるケースが増えています
- 投資家からの関心:環境に配慮した企業への投資(ESG投資)が拡大し、企業の気候変動対応が投資判断の重要な要素になっています
- 消費者の意識変化:環境に配慮した商品やサービスを選ぶ消費者が増えています
- 規制対応:世界中で気候変動関連の規制が強化されており、将来的な対応に備える必要があります

デジタル化やDXが進む昨今、「データで見えないものは管理できない」という言葉を耳にすることもあります。CO2も同じです。まずは測って「見える化」しないと、削減のしようがありません。
でも、CO2排出量を測るといっても、「どうやって測ればいいの?」という疑問が湧きますよね。実は、CO2の測り方がバラバラだと正確な比較ができません。A社とB社が別々の方法でCO2を測っていたら、どちらが環境に優しいか判断できないのです。
そこで登場するのが「GHGプロトコル」です。
GHGプロトコルとは?CO2を測る「ものさし」
GHGプロトコル(温室効果ガスプロトコル)は、企業や組織が温室効果ガス(主にCO2)の排出量を計算するための国際的な標準ルールです。簡単に言えば、「CO2を測るものさし」です。「GHG」とは「Greenhouse Gas(温室効果ガス)」の略称です。CO2だけでなく、メタンや一酸化二窒素などの温室効果ガス全般を含みますが、本記事ではわかりやすさのためにCO2と表現しています。
CO2排出量は測り方がバラバラだと正確な比較ができません。
- あるメーカーが「当社の製品は年間CO2排出量100トンです」と言っても、測り方を変えれば150トンになることもある
- 去年と今年で測り方が違うと、本当にCO2が減ったのか、単に計算方法が変わっただけなのかが分からない
- 投資家が「環境に配慮した企業に投資したい」と思っても、どの企業が本当に環境負荷が低いのか判断できない
たとえば、取引先から「御社のCO2排出量を教えてください」と突然言われて、社内でいろいろ調べてみると、部署によって計算方法がバラバラで、統一した数字を出せないという状況にもなりかねません。こういった混乱を避けるためにも、共通のルールが必要になります。

GHGプロトコルは、世界中の企業がCO2排出量を同じルールで計算できるようにするための「共通言語」です。法律で強制されているわけではありませんが、世界中で最も広く使われている標準的な方法として定着しています。
CO2はどこから出てる?scope1・2・3を理解しよう
GHGプロトコルでは、CO2排出量を「scope1」「scope2」「scope3」という3つのグループに分けています。これは、排出源の種類と企業の責任範囲を明確にするためです。
ゴミに例えると「自分の家から直接出るゴミ=scope1」「電気を使うことで発電所から出るゴミ=scope2」「自分が購入した製品が、製造されて自分の手元に届くまでに出たゴミ=scope3」というように分けて考えるようなものです。
この3つのscope、最初は少し複雑に感じるかもしれませんが、実例を交えながら違いを確認していきましょう。
scope1:自社から直接出るCO2
scope1は、企業が直接排出するCO2のことです。言い換えれば、自社の敷地内で化石燃料を燃やすことで発生するCO2です。
- 工場のボイラー:重油や灯油を燃やして蒸気を作る
- 暖房設備:灯油やガスを燃やして暖房する
- 社有車:ガソリンや軽油を使って走る
これらは企業が直接コントロールできる排出源なので、最も基本的な排出量と言えます。たとえば、省エネボイラーに替えたり、社有車をハイブリッドカーに替えたりすれば、直接削減できます。
scope2:電気や熱の使用で間接的に出るCO2
scope2は、企業が購入した電気や熱(蒸気など)を作るときに発生したCO2のことです。
- 電力の使用:オフィスや工場で使う電気
- 購入した熱や蒸気:他社から供給を受ける熱エネルギー
これらは自社の敷地内からは直接CO2が出ていませんが、電気を使えば使うほど、電力会社の発電所で石炭や天然ガスが燃やされ、CO2が排出されることになります。
例えば、工場の機械を動かすために電気を使うとき、機械自体からはCO2は出ませんが、その電気を作るために発電所では石炭などが燃やされています。つまり、間接的にCO2排出の原因となっているわけです。
コンビナート地域などでは、自社のタービンを回すために隣の工場で作られた蒸気をパイプラインで受け取るようなケースもあります。このような購入した熱エネルギーもscope2に含まれます。
scope3:その他のすべての間接的なCO2
scope3は、上記以外のすべての間接的なCO2排出のことで、企業のバリューチェーン全体に関わる排出量です。実は、多くの企業にとって、最も量が多いのがこのscope3です。
- 原材料の調達:製品の原材料を作るときに出るCO2
- 輸送・配送:原材料や製品を運ぶトラックなどから出るCO2
- 出張・通勤:従業員の出張や通勤で使う交通機関から出るCO2
- 製品の使用:販売した製品を顧客が使用することで出るCO2
- 廃棄・リサイクル:製品が捨てられたときに出るCO2
GHGプロトコルでは、scope3をさらに15のカテゴリーに分けています。範囲が広いため、データ収集や計算が最も難しい部分です。
例えば、自動車メーカーの場合、トヨタ自動車の例では、scope3の排出量が全体の98%以上を占めています。特に「販売した製品の使用」(カテゴリー11)、つまり販売した車が走行中に排出するCO2が最も多くなっています。トヨタの場合、scope3の中でも「販売した製品の使用」が圧倒的に多く、次いで「購入した物品とサービス」(カテゴリー1)が多いです。
scope1.2.3に関する詳しい解説はこちら
「正しく測る」ための5つのルール
GHGプロトコルでは、CO2排出量を正確に測るための5つの基本原則を定めています。これらは「測定の品質」を確保するための重要なルールです。
- 妥当性(Relevance)
「目的に合った測り方をしているか?」という原則です。自社の事業活動とCO2排出の関係を適切に反映した測定方法を選ぶということです。例えば、自社工場内の電力使用を測る際、他社に貸しているスペースの電力は含めるべきか除外すべきかなど、境界を適切に定義する必要があります。
- 完全性(Completeness)
「必要なものをすべて測っているか?」という原則です。
関連するすべての排出源を含める必要があります。例えば、複数の事業所や子会社がある場合、一部だけではなくすべての排出源を対象にする必要があります。ただし、完全に網羅するのが難しい場合は、重要度の高いものから優先的に取り組むアプローチも認められています。
- 一貫性(Consistency)
「毎回同じ方法で測っているか?」という原則です。
年度ごとに測定方法を変えると正確な比較ができません。例えば、ある年は「出資比率に応じた排出量」を計算し、翌年は「取引関係に基づく排出量」に変更すると、CO2排出量が突然減ったように見えるかもしれませんが、それは実際の削減ではなく単なる計算方法の変更によるものです。
- 透明性(Transparency)
「測り方を明確に説明できるか?」という原則です。
どのようなデータをどのように計算したかを明確にする必要があります。投資家や取引先などの第三者が、その排出量データの信頼性を確認できるように、計算方法や前提条件を開示することが重要です。
- 正確性(Accuracy)
「できるだけ正確に測っているか?」という原則です。
例えば、電力の排出係数(1kWhあたりのCO2排出量)は毎年更新されるため、常に最新のデータを使用する必要があります。古い係数を使い続けると、実際の削減効果が反映されなくなります。
これらの5つの原則を意識することで、より信頼性の高いCO2排出量データを算定することができます。
scope別の算定アプローチ
scope1の算定方法
scope1は、直接的な燃料使用量に対して排出係数を掛けて計算します。scope1は比較的算定が簡単です。
例えば、灯油を使用した場合:
- 灯油1キロリットル当たり2.5トンのCO2を排出
- 100リットル使用した場合は、2.5 × 0.1 = 0.25トンのCO2排出量
各燃料には排出係数が定められており、温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)などでも公表されています。例えば:
- ガソリン:1キロリットル当たり2.29トンのCO2排出量
- 灯油:1キロリットル当たり2.5トンのCO2排出量
- 軽油:それぞれの排出係数が定められています
引用元:温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver6.0) (令和7年3月) 第Ⅱ編 温室効果ガス排出量の算定方法(環境省)
scope2の算定方法
scope2も、電気使用量に電気事業者の排出係数を掛けて計算します。
例えば:
- 電力会社(例:東京電力エナジーパートナー)の排出係数が0.39kg-CO2/kWh
- 年間100,000kWhの電力を使用した場合
- 100,000 × 0.39 ÷ 1,000 = 39トンのCO2排出量
電力の排出係数は電力会社や契約メニューによって異なり、毎年更新されます。環境省や経済産業省から公表される最新の係数を使用することが重要です。
scope3の算定方法
scope3は最も複雑で、15のカテゴリーごとに異なる算定方法があります。環境省が定めるデフォルト値を使用することが一般的です。
例えば、カテゴリー1(購入した製品・サービス)の場合:
- 環境省の産業連関表データベースに基づくデフォルト値を使用
- 例:米の購入であれば、100万円あたり6.26トンのCO2排出量
- 年間500万円分の米を購入した場合、6.26 × 5 = 31.3トンのCO2排出量
しかし、このような金額ベースの計算では、取引先の実際の削減努力が反映されません。より正確に測るためには、実際のサプライヤーからのCO2排出データを入手することが望ましいです。
データ収集と社内体制の整え方
必要なデータと収集方法
scope1・2のデータ収集は比較的シンプルです。
- scope1:燃料購入量の請求書や記録(リットル単位)
- scope2:電力使用量の請求書(kWh単位)
scope3は複雑で、さまざまなデータが必要です。
- 購入した物品の金額や量
- 輸送業者の走行距離や車両タイプ
- 従業員の通勤・出張データ
- 販売した製品の使用データ など
社内体制の整え方
効果的なCO2排出量算定のためには、部門間の連携が不可欠です。
- 経営層の関与:まず経営層からの号令により、全社的な協力体制を構築しましょう
- 部門間連携:サステナビリティ推進部署と調達部門、総務部門、営業部門など関連部署の連携が必要です
- データ収集体制:定期的なデータ収集の仕組みを構築し、担当者を決めましょう
- 検証体制:算定結果を複数人でチェックする体制を整えましょう
まとめ:GHGプロトコルを理解することの重要性
CO2排出量の「見える化」は、環境対応の第一歩です。GHGプロトコルを理解し、自社のCO2排出量を測定することで、次のようなメリットが得られます。
- 現状把握:自社のCO2排出がどこからどれくらい発生しているかを知ることができる
- 削減機会の発見:排出量が多い箇所を特定し、効果的な削減策を講じることができる
- ステークホルダーとの信頼関係構築:投資家、取引先、消費者に対して環境への取り組みを定量的に示すことができる
- 将来のリスク対応:炭素税や排出規制などの将来的なリスクに備えることができる
- 競争優位性の確保:環境対応が進んでいる企業は、市場での評価も高まりつつある
CO2排出量の算定は難しそうに思えるかもしれませんが、最初からすべてを完璧にする必要はありません。まずはscope1と2の排出量から始め、少しずつ範囲を広げていくことをお勧めします。
例えば、具体的な第一歩としては、
- 燃料使用量と電力使用量のデータを収集する
- 適切な排出係数を調べる(環境省や経済産業省のウェブサイトから入手可能)
- 簡単な掛け算でscope1・2の排出量を算出する
- 重要なscope3カテゴリーを特定し、段階的に算定範囲を広げる
「百聞は一見にしかず」という言葉通り、実際に測ってみることで多くの気づきが得られます。「うちはあまりCO2を出していないはず」と思っていても、実際に測ってみると意外な排出源が見つかるかもしれません。
次回は、実際にどうやって自社のCO2排出量を測るか、その具体的な方法を実例を交えてお伝えします。